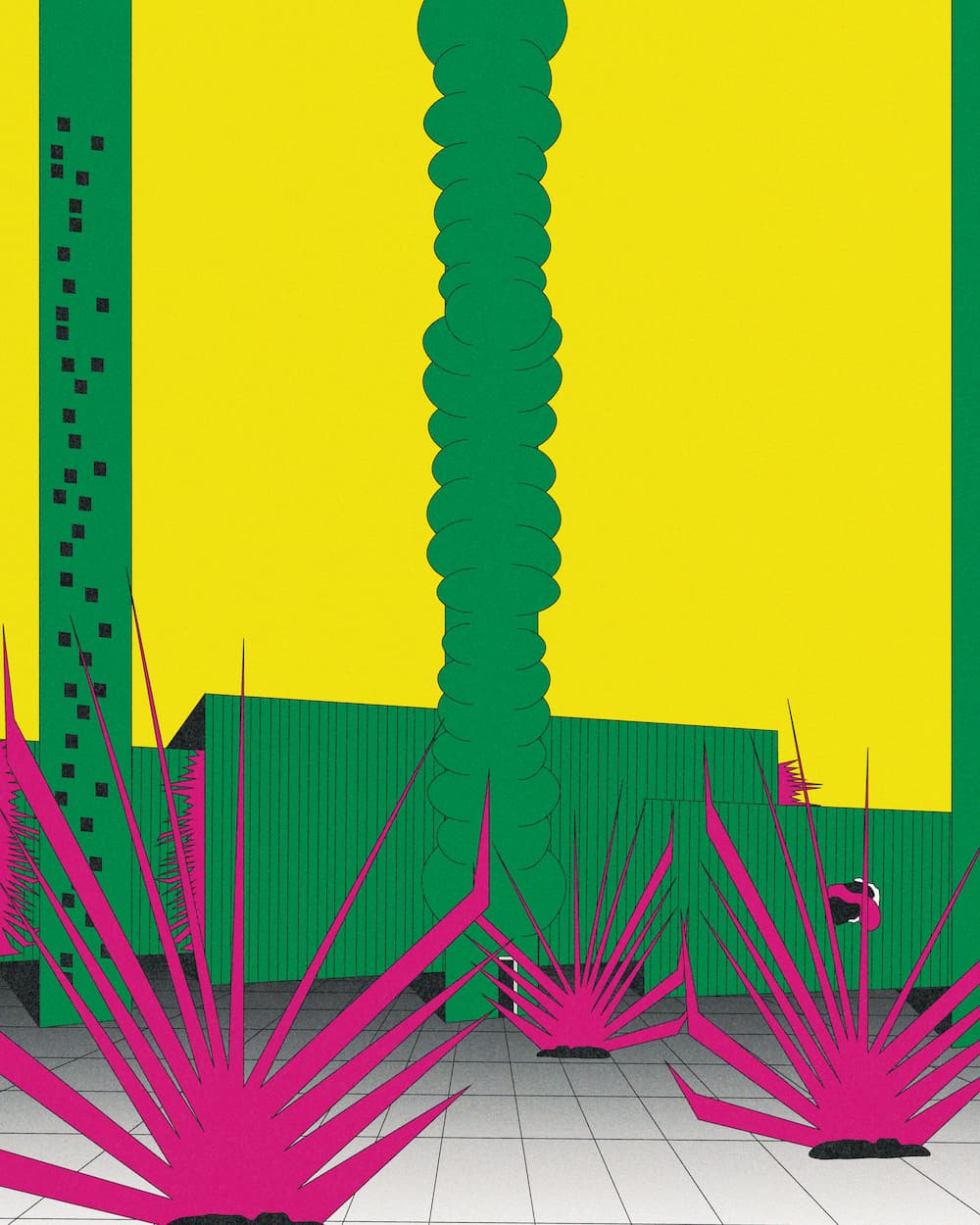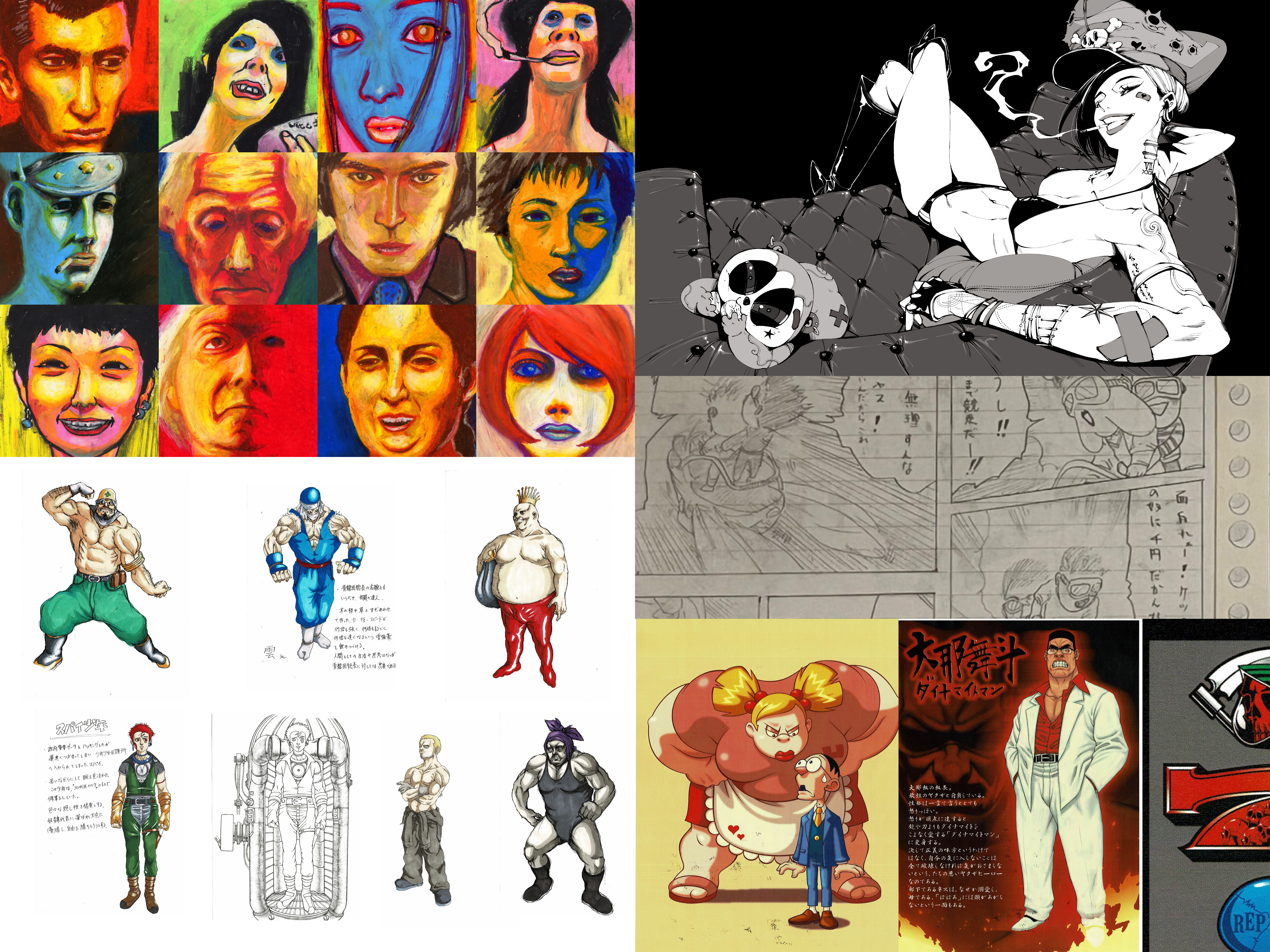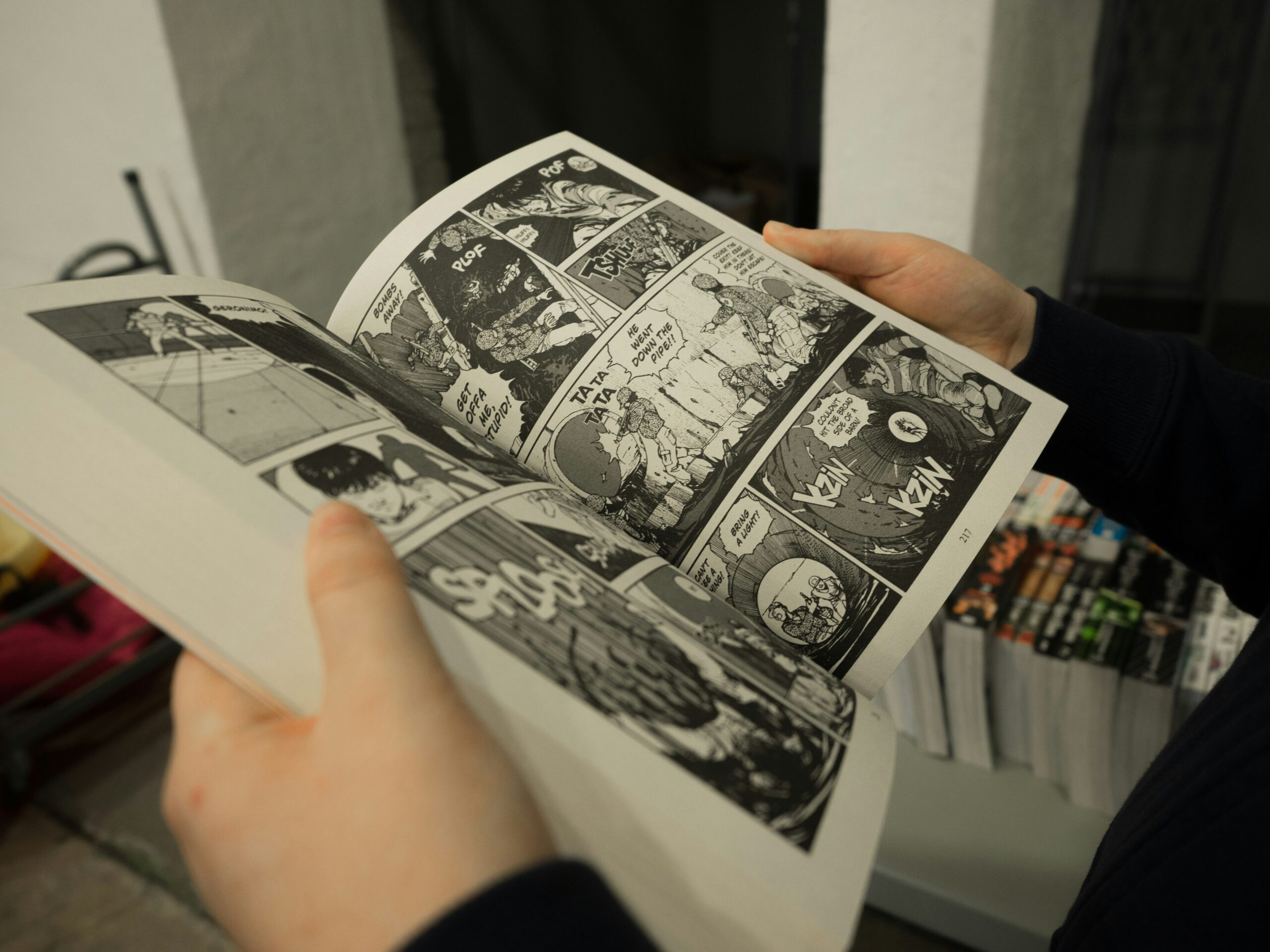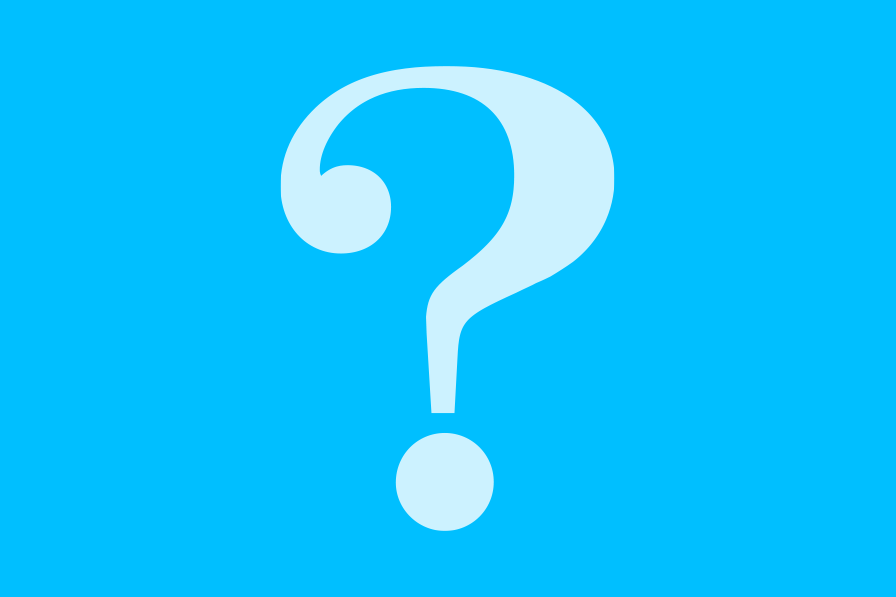2010年、低迷していたユニバーサルスタジオジャパンに入社したマーケターの森岡毅は、それまでの映画に特化したテーマパークというUSJのイメージを刷新し、数々のアニメや漫画とのコラボレーション企画を打ち出してきた。入社当時の年間来場者数が約730万人だったのに対し、2016年度には、およそ2倍である1460万人の来場を達成。目覚ましいV字回復を成し遂げた。その間斬新なアイデアを打ち出し続けたが、この快進撃にアニメや漫画とのコラボレーションが一役買っているのは言うまでもない。
また、ユニバーサルスタジオハリウッドでは、2025年の4月よりUNIVERSAL FAN FEST NIGHTSを初開催。同イベントでは、日本からは『ONE PIECE』、『呪術廻戦』が参加し、テーマパークでしか味わえない特別な体験を味わうことが出来る。
だが、分野を跨ぐ越境は、なにもマーケターの専売特許ではない。先に述べたコラボレーションが生み出す経済効果は自明の事だが、越境による異種混交は今に始まったことではない。人類のまだ見ぬ景色への欲望は、およそ180万年前にアフリカから踏み出した最初の一歩目から、アポロ11号に乗ったニール・アームストロングの月面歩行、そして現在までの系譜の中で、そのダイナミズムを加速化させている。轟轟と走り出したテクノロジーの波は収まることを知らない。
そしてその流れはアートの世界にも飛び火。
「高尚なアート」はその姿を変え、形を変え、あちらこちらに散開した。
今やアートは至るところに、お、言った側から…。
アートによって拡張するIPコンテンツ
もはや知らない人はいないであろう、『ドラゴンボール』。
2019年にはコラージュアーティストである河村康輔とタッグを組み、ユニクロのグラフィックTシャツラインである「UT」から「ドラゴンボールUT」を発売。イラストを一度裁断し再構築するというシュレッダーデザインによって、新たな表現として生まれ変わった孫悟空の必殺技「かめはめ波」など見どころはたくさんだ。
先の河村康輔は2017年には渋谷PARCO企画である『AKIRA』アートウォール・プロジェクトを展開。『AKIRA』作者である大友克洋とタッグを組んだ同企画は、当時建て替え工事中であった渋谷PARCOの工事仮囲いをキャンパスとし、「ただの壁」だった場所をパブリックアートとして彩った。IPコンテンツとアートのコラボレーションが起爆剤となり、都市開発に新しい風を吹き込んだのだ。カニエ・ウェストもお忍びで来日するなど、大変話題を呼んだ事は記憶に新しい。
先の事例同様、『ポケットモンスター』も精力的なコラボレーションを展開している。2020年には、現代アーティストのダニエル・アーシャムとのコラボレーションを実現。「1000年後、3020年に化石になって発掘されたポケモン」を彫刻作品として制作するアートプロジェクトで、ピカチュウやイーブイなど、馴染みのポケモンたちが化石となって展示された。
ポケモンはその後も同氏とのコラボを重ね、それまでの作品を一挙にまとめた『ダニエル・アーシャムのポケモン図鑑』が2022年、美術出版社から発売。24種の彫刻ドローイングに加え、ペインティングなど91作品を収録している。
さらに2024年、ポケモンは「工芸」とのコラボレーションにも挑戦。人間国宝である桂盛仁はじめ、総勢20名のアーティストがポケモンと「工芸」の掛け算を見事にやってのけた。本展示では、日々を彩る器、着物や帯留など粋な装いに誘い込まれたポケモンたちを見ることが出来る。2025年は日本国内3箇所で巡回するというから見逃すわけにはいかない。
国内外を問わず大人気の『鋼の錬金術師』が2017年にコラボしたのは、墨絵師である御歌頭氏だ。墨絵師とは読んで字の如く、墨で絵を描くアーティストのこと。かの水墨画は墨絵の一種であり、中国での修行後帰国した雪舟によって日本独自の水墨画が確立された。そうした歴史深い墨絵において、御歌頭氏は中でも戦国武将と城を中心に描くアーティストだ。それに加えアニメや映画、スポーツの墨絵化でも知られており、彼もまた異なる文脈を見事に繋ぎ合わせている。本企画では、『鋼の錬金術師』の人気キャラクターを墨絵で描き、それを和紙にプリントしたグッズを販売。日本特有の歴史深い文化とのコラボレーションは、国民的アニメを新鮮なイメージで再解釈している。
このように、今やIPコンテンツとアートのコラボレーションはあちらこちらで同時多発的に発生している。慣れ親しんだあの作品やこの作品の新鮮な姿を見ていると、移ろいゆく時代の中でナニかが蠢く気配を感じる。アートも、IPも、さながら生き物かのように、これからも変わり続けるだろう。その姿を、1ファンとして、見届けていきたい。