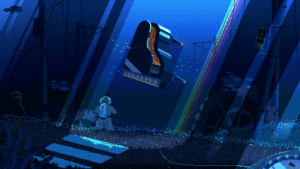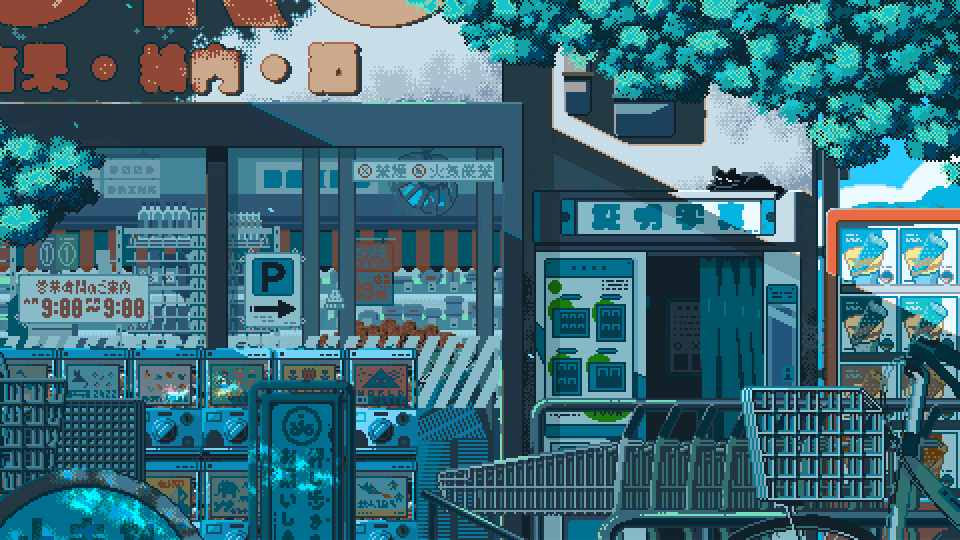「namco TOKYO」と言えば、新宿にあるゲームセンター。運営するのはバンダイナムコアミューズメントだ。ゲームセンターのイメージが強い同社だが、この他にも様々な取り組みを行っている。例えば「VS PARK」では、テレビのバラエティ番組のように大掛かりで、走ったり、投げたり、打ったり、跳んだり。様々なエンターテインメント要素をふんだんに盛り込んだアクティビティを楽しむことができる。
今回は、多方面に事業を拡大しているバンダイナムコエクスペリエンス経営企画部経営戦略課に所属する松村氏に話を伺った。

B- バンダイナムコエクスペリエンスの経営企画部経営戦略課とは具体的にどのような仕事をするのですか?
松村- ビジネスの種を見つける仕事ですね。既存事業ではない新規事業を検討する課になります。
B- その事業の一環で、アートに目を付けられた?
松村- いや、正直言って、アートとのコラボは偶然なんです。偶然というか、ご紹介いただいたのがきっかけです。実際にGAAATさんの作品を見た瞬間に、IPとの親和性だったり、これまでにない価値を提供できそうだな、と。そこから前向きにお話しさせて頂きました。

B- いざアート作品を作るにあたって、どうして『PAC-MAN』だったのですか?
松村- 単純に僕が好きだからっていうのもあるんですけど、今回、まずはじめに顧客ターゲット層として思い浮かんだのがインバウンドだったんですね。
B- 確かに、海外での日本のアニメ、漫画の人気すごいですからね。
松村- コロナでの自粛期間中に、すごい配信プラットフォームが伸びたんですね。その間に日本アニメってすごい認知度が上がったんですよ。
B- なるほど。
松村- 特にアメリカでは『PAC-MAN』人気ってすごいんです。熱狂度がすごくて。この『PAC-MAN』を正しい形で魅力的なコンテンツにすることができれば、絶対多くの人に共感してもらえるだろうなと思いました。
B- 最終的に作ったのはMCA(メタルキャンバスアート)作品でしたよね?
松村- そうですね。
B- それはどうして?
松村- IPキャラクターって、機能的な商品が多くて、例えばボールペンにキャラクターが描かれている物とか、ドリンクのパッケージにキャラクターがついてるとか、そういう付加価値。
B- いわゆる、副次的なものというか。
松村- 情緒的なものでいうと、フィギュアだったり、ぬいぐるみとか、アクリルスタンドみたいなものがメインだと思うんです。 何かもうちょっと、キャラクターを生活に馴染ませるというか、憧れられる形で展示できるものがないか、ちょうど探してたところだったんです。 そんな中で、パッと見て価値が伝わる、これであればお金を出してもいいなと思うようなものだったので、試してみたいと思いました。

B- 合わせて体験型空間エンターテインメントを企画されたんですね。
松村- そうですね。
B- 生演奏を聴きながら踊れて、神輿を担げる。アートも見て、尚且つ買えるイベントだったと聞きました。
松村- これもインバウンドに対して、うちのコンテンツを組み合わせた音楽イベントみたいなものができれば面白いなと思ったのが走りです。ただ音楽聴いて飲めるイベントじゃ面白くないよねっていうので、アイディアを出していく中で、例えば神輿担げるってどう?みたいなアイディアが出てきたんです。その場では、いやないでしょって思ったんですけど、その日帰った夜に、ずっと神輿のことが頭から離れなくて。確かにおもしろいなと。それで試しに作ってみたっていう感じですね。

B- 音楽はどうしてシティーポップにしたのですか?
松村- これもアメリカでとてつもない認知度と熱狂度のあるシティーポップを掛け合わせるっていう狙いです。 あとちょっと裏話ですけど、本当は『PAC-MAN』で一つの音楽を作りたいなって思ったんです。イベント当日に、三、四十分ぐらい生演奏の尺がある中で、『PAC-MAN』っていうと、1980年発売のゲームなのでそんなに音源がないんですよ。その三、四十分持たせるような音源素材が存在してなかった。
B- なるほど。
松村- 『PAC-MAN』が生まれた当時1980年代のシティーポップと、『PAC-MAN』のSE(ゲーム内の効果音)を効果的に使ってやりましょうっていうのを、今回入って頂いた音楽プロデューサーの方に提案していただいて、面白そうだなと決めました。
シティーポップの生演奏を聴きながらお酒を飲む。加えて神輿を担げてアートも見れる。買える。一見なんの繋がりもないように思えたイベントの狙いや内実を聞けたところで、後編では、そもそも、どうしてこのイベントを企画したのか、その背景を伺えればと思います。
PAC-MAN™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.