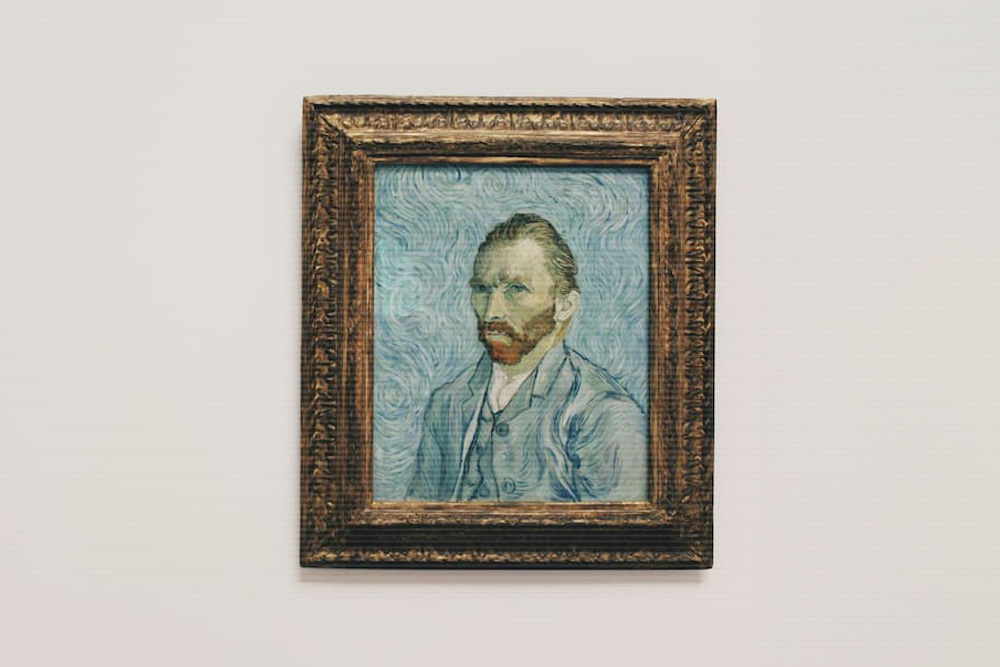書評家・三宅香帆氏による鋭い分析が話題の『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(集英社)。昨年夏に発売されるやいなや、年間ベストセラー1位(新書ノンフィクション/日販・トーハン・オリコン調べ)の大ヒットだ。本を読みたいけれどなかなか手に取ることができないーー。そんな心当たりがある人が多いのだろう。本はもちろん、趣味に費やす時間や余裕がないのが現代の辛いところ。
そんな今だからこそ、絵を描くことをお勧めしたい。何を言ってるんだ、と思うかもしれないが、紙もペンも絵の具も要らない。iPadひとつでイギリスの巨匠、デイヴィッド・ホックニーと同じように描けると聞いたら、話が変わってくるはず。
実際どうやるのか、なぜiPadなのかは後編で紹介するとして、まずはホックニーの辿った道のりからご紹介。
デイヴィッド・ホックニー(1937年〜)は名実ともに現代を代表する画家のひとりだ。金色の髪に丸メガネ、キャッチーなファッションがトレードマーク。そんなオシャレでポップな出たちとは裏腹に、美術史学や文学の見識も深く、多数の著作も著している。

ここ日本では、東京都現代美術館で、2023年7月に「デイヴィッド・ホックニー展」が開催された。27年ぶりとなる大規模個展とあって訪れた方も多いのではなかろうか。120点余が展示された展覧会では、作家本人が「私の人生の大半をたどることができます」と語ったように、その出自となるポップアート文脈の作品からリトグラフ作品、有名な「肖像画シリーズ」、3000枚に及ぶ写真をコンピューターで解析し3DCGを生成するフォトグラメトリや、iPadで取り組んだ全長90メートルにもわたる新作絵画までも展示。ホックニーの多岐にわたるこれまでの活動が把握できるものだった。
彼の出自を簡単に振り返る。1937年、イギリス・ブラッドフォードに生まれたホックニー。ロンドンに出て、王立美術学校で学ぶ傍らブリティッシュポップ(イギリスにおけるポップアート)の旗手たちと出会う。在学中からその才覚を現し、二十代半ばでアートシーンから注目を浴びる存在となった。数々の個展を成功させながらも、憧れを抱いたのはLAの明るい空。64年には単身アメリカ・ロサンゼルスへ拠点を移す。
彼が度々モチーフにする「プールサイド」が描かれたカリフォルニアの風景シリーズもこのころに制作されたものだ。1972年の作品『芸術家の肖像(2人の人物のいるプール)』は2018年に存命画家における当時の最高額である約102億円で落札されたことも大きなニュースとなった。
魅力は、表現の幅広さと、探究精神。自身の出自となるポップアートと抽象表現主義からはもちろん、パブロ・ピカソやジョルジョ・ブラックらキュビスムの複雑な画面構成や、印象派のような戸外制作も行う。さらには日本の石庭鑑賞の伝統(京都の龍安寺に訪れた際の驚きを作品にしている)や絵巻物からもヒントを得て作品に取り入れるなど、派閥や流派、特定の表現技法にこだわらない姿勢が特徴的だ。
また、写真のコラージュや3D、舞台美術など表現方法も変われど、デビュー以来、ホックニーに対する高い評価と人気は現在に至るまで揺るぎない。
カメレオンのようにアート作品を作り続けるホックニーだが、“軸”がないわけではない。彼が大切にしていたのは自分の目に見えるもの(リアル)をよく見て描くこと。現実世界をよく見て、感じたことを描こうとするシンプルな気持ちだ。彼が「見る」ことのリアリティや意味を追求してきたという点では、その人生は一貫している。
そんなホックニーがなぜiPadで絵画を描くことに行き着いたのか。問いの答えは後編で。

.jpg)