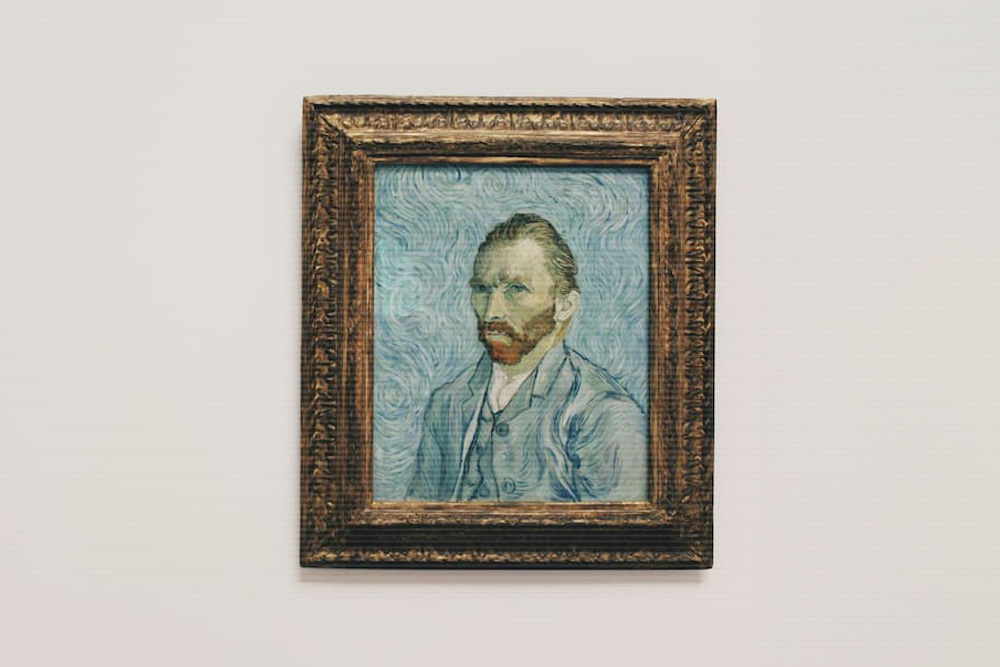「僕から一個だけ。憧れるのをやめましょう」から始まった大谷翔平の言葉は、2023年、ベースボールクラシック(WBC)決勝の舞台を前に、侍ジャパンの気を引き締めるには十分だった。前回王者であるアメリカを3-2で下し、実に14年ぶり3度目の優勝。悲願の世界一奪還を成し遂げたのだ。
試合前、円陣での声出しを務めた大谷の言葉は次のように続く。
「憧れてしまっては超えられないので、僕らは今日超えるために、トップになるために来たので。今日一日だけは彼らへの憧れを捨てて、勝つことだけ考えていきましょう。」
「謙虚な日本人」というレッテルを、この日だけはそっと剥がして果敢に立ち向かった侍ジャパンの勇姿は、今なお鮮明だ。だが、戦いの場はスタジアムに限った話じゃない。野球のような熱狂や派手さはないかもしれない、いや、ところがそんなこともない。
今回は、時にド派手に、しかしリスペクトは忘れず、伝統文化に挑戦する人たちを紹介していく。
独自スタイルで切り拓く新たな茶道
松村宗亮は、茶の湯の基本を守りつつ、現代にあった独自のスタイルを構築している茶人だ。松村は学生時代にヨーロッパを放浪。その時に自分は日本人でありながら日本文化を知らないということに気がつき、帰国後に茶道に華道、習字を始めた。中でも「お茶」に面白さと可能性を見いだし、のめり込んでいく。
「ルールの間にある自由さ」が楽しいと語る通り、彼の活動は自由、もっと言うと無茶苦茶にも見える。と言うより「無茶苦茶」は、彼が会長を務める会社の名でもある。
世界的なデザインの祭典である「Dubai Design Week 2023」では、「アラビ庵」での茶会をプロデュース。茶室はその土地の緯度から形状を導き出し、地域の生ゴミを「食品コンクリート」として建設するなど、展示国であるドバイの文化にちなんだ企画は大変話題を呼んだ。
コンテンポラリーアートや舞踏、ヒューマンビートボックス、漫画などとの積極的なコラボレーションにも見られる彼の独自性は、ある意味では必然だった。
それは、無名かつ初代といういわばハンデを持って、伝承文化である茶道の世界に飛び込んだ彼の生き抜く術でもあったわけだ。利休の時代から脈々と続く、創造性や精神性、爆発力を忘れずに、彼の活動は納まるところを知らない。
言語学のズレを焦点に
伝統に則り、拡張していく動きは、書家の山本尚志にも共通している。
「モノにモノの名前を書く」ことを立脚点として、書と現代アートを行き来する山本。
彼は「書」が言語であると想定しつつも、言語学とは元来西洋の文脈であり、漢字やひらがな、カタカナには対応していないところに目を付ける。
例えば、リンゴという物質を表す英単語は「apple」。
これが日本語の場合は「リンゴ」や「林檎」、「りんご」…。
日本人からすると、何を当たり前なことを、という話だが、海外の人からすると、
「…?」
山本は、西洋の言語学と、日本や漢字文化圏の言語学のこうした明らかなズレに焦点を当てた。
また、同氏は2018年より「ART SHODO」を提唱。現代書の認知と書家の発掘を目指した組織で、今では100人ほどの規模にまで成長し、様々な作家を輩出している。
山本から広がる現代アートとしての「書」。その盛り上がりから目が離せない。
と思っていたが、街中で見かけたスニーカーには、思わず目を奪われた。
VANSの「OLD SKOOL」を彩るのは、遠目にみると迷彩柄だが、よくよく目を凝らすと…盆栽!
盆栽のニュースクール
平安時代に中国から伝わったとされる盆栽は、日本で独自の発展を遂げた。銀閣寺を建立し、文化的側面でもよく知られる室町幕府8代将軍足利義政も盆栽を育てていたそう。
そんな、いわゆる手の届かない盆栽のイメージを刷新したのが、小島鉄平だ。彼が代表を務めるTRADMAN’S BONSAIでは、先のVANSをはじめ、様々なコラボレーションを実現。
彼もまた松村宗亮同様、事のきっかけは海外での出来事だった。当時アパレルバイヤーとして米国を巡っていた小島が目にしたのは、曲解された「盆栽」の姿。自慢げに見せられたそれは、鉢合わせも剪定もできておらず、幹にペンキを塗ったものまであったという。
松村と事情が異なるのは、彼は幼少期から盆栽に触れていた点。
服の裾からチラリと見えるタトゥーや、ストリートカルチャーやファッションを好んでいるパーソナリティからわかるように、幼少期から盆栽の「カッコよさ」に惹かれていたという。海外で曲解されていた「盆栽」のカッコを外し、その素晴らしさを、国内外に伝える小島。
彼もまた「オールドスクールがあってのニュースクール」と語っている。
登場した3人に共通するのは、先人を尊びながらも、果敢に挑戦する姿勢。進化論にもわかるように、移ろいゆく時代の中で淘汰された種は数えきれない。伝統文化もまた、新陳代謝を繰り返すことで時代を超えてゆく。
そしてこここそが、伝統文化の最前線だ。