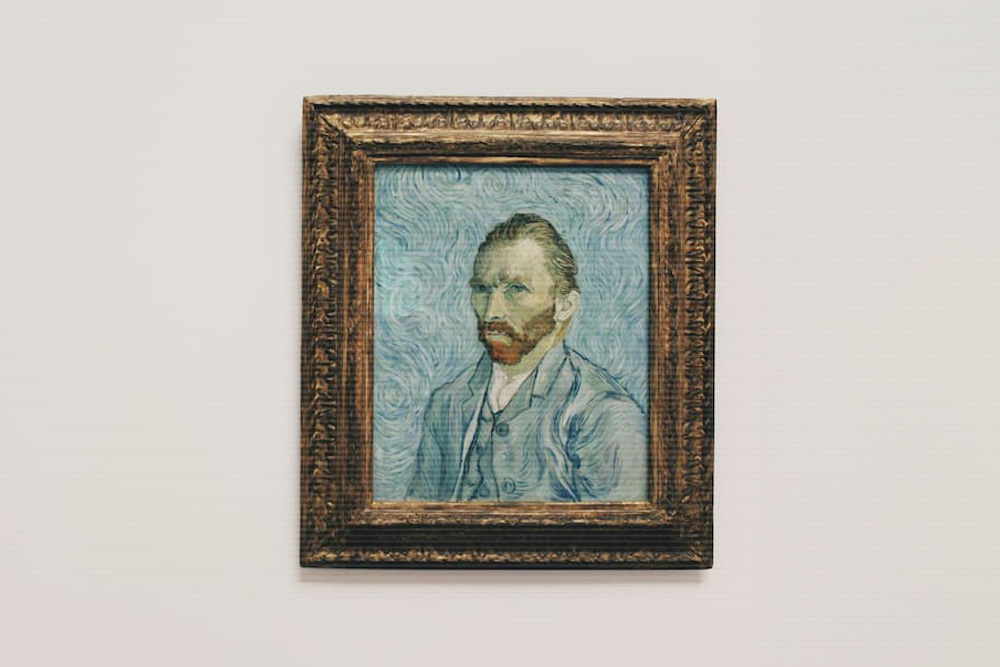民藝とは何かをご存知だろうか。民藝と聞くとアートの文脈からはかけ離れた、お土産のようなイメージもあるが、実はさまざまな時代のアーティストやデザイナーたちを虜にしてきた。民藝という言葉を生み出した「民藝運動」とは、歴とした日本発の芸術運動なのだ。民藝運動は国内外の工芸・美術・思想の世界を中心に瞬く間に広がり、その影響は現代の作家たちにも与え続けられている。民藝の愛好家たちはみな、使っていくことで民藝の奥深さを身をもって知ってきた。そう、民藝とは最も身近な”使える”アートなのだ。
民藝の本質:職人の美、世界を魅了する日本の生活文化運動
民藝運動とは、1926年に柳宗悦・河井寛次郎・浜田庄司らによって提唱された生活文化運動のことだ。当時の工芸界の主流は装飾的な作品。柳たちは、名も無き職人の手から生み出された地域特有の生活道具を「民藝」と名付け、生活の中にこそ美しさがあると考えた。
2024年には、東京・森美術館で「シアスター・ゲイツ展:アフロ民藝」が開催されたのも記憶に新しい。世界でもっとも影響力のある100人*のアーティストにも選ばれている現代アーティスト、シアスター・ゲイツが、自らの黒人としてのアイデンティティと、日本の民藝運動における思想を融合した「アフロ民藝」が注目を集めた。
※Power 100 – ArtReview

民藝の現在:伝統と革新が交差する、新たなアートの形
さて、使ってナンボの民藝。私たちの暮らしにどう活かしていけばよいだろうか。東京・青山にあるARTS & SCIENCEはいち早く民藝の世界観をファッションに落とし込んだセレクトショップで海外からのファンも多く訪れる。
丁寧に選び取られた、食器やラグなどの日用品に加えて、古布・草木染めなどを使った洋服やバッグをスタイリッシュに提案している。

世界が注目する民藝の世界。スペインのラグジュアリーファッションブランドであるLOEWEは、クリエイティブディレクターであるジョナサン・アンダーソン氏の下で定期的にLOEWE CRAFT PRIZEというイベントを開催しており、民藝の流れを汲む日本およびアジアの工芸作家たちも多くノミネートされている。
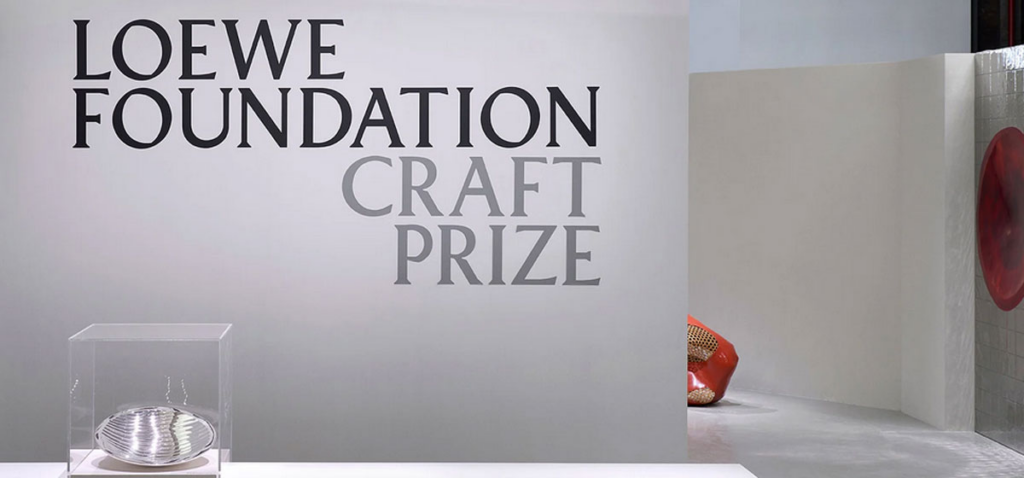
ジョナサンはJWアンダーソンのデザイナーでもあり、近年ではユニクロとの継続的なコラボレーションを実施するなど、幅広い活動を行っている。ラグジュアリーなものから、手に取りやすいものまでをデザインしている彼の姿勢そのものが、民藝の思想に通じるところもある。
日本から世界へ:民藝がつなぐアート新たな一面
最後に日本から世界に民藝を紹介しているtatami antiqueを紹介しよう。複数人のディーラーからなるtatamiは、日本の土産物屋の大定番!・ペナントのコレクションから民家の木札、骨董品にいたるまでさまざまな民藝品を日本や海外で展示・販売している。(オンラインショップからも購入できる)
民藝は国境を越え、さまざまな人々に愛されるアートになりつつある。たとえばこけしは”KOKESHI doll”として知られている。日本各地に存在するこけしは、一つとして同じスタイルがなく、最近ではキャラクターやブランドとコラボしたコレクターズアイテムまで存在している。一つ集めると、また一つ集めたくなる。そんなマニア心をくすぐるところも民藝の大きな魅力だろう。(かく言う私も土鈴をコレクションしている。振るとカラカラ音が鳴って楽しい。笑。)
民藝にはまだ価値が与えられていないものもたくさんある。そんなものに自分だけの価値を見出すロマンに溢れていることが、民藝を愛でることの楽しさだ。
モノでいっぱいの世の中で、私たちは何を選びとるのか。民藝には消費社会への疑問に対する答えがわずかながら隠されている気がする。